こんにちは、みみたまボーイです。
突然ですが、アメリカの入国審査に不安を感じたことはありませんか?特に「別室送り」になるという話を聞くと、なおさら緊張しますよね。
実は海外駐在員生活10年の私でも、アメリカの入国審査は毎回ドキドキ。
台湾や韓国なら何も聞かれずに入国できますが、アメリカでは質問攻めの末、ちょっとしたことがきっかけで別室送りに…。この5年で私自身は3回、家族も1回体験しています。
最初の別室送りでは本当にビビりましたが、今ではちょっと慣れました(笑)。そこで今回は、アメリカの入国審査で私が経験した「別室送り」の実体験をお届けします。
別室の雰囲気や突破方法、そして乗り継ぎフライトへの影響など、これからアメリカへの入国を控えている方の参考になれば幸いです!
では、さっそく始めましょう!
です。
アメリカの入国審査は厳しい?

まず、アメリカの入国審査は他の国の入国審査と比較して厳しい事を認識しておきましょう。正確には「質問が多い」と言うべきでしょうか。
これは、アメリカが「入国しても問題のない人物かどうか」を見極めるために行っているプロセスです。審査官の職務姿勢としては至極当然なのですが…
 ライオンさん
ライオンさんこっちは困る(笑)
入国審査でよく聞かれる質問
アメリカの入国審査では、突飛な質問はありませんが、以下のような基本的な項目が英語で尋ねられます:
- 滞在目的
- 滞在先、期間
- 職業
- 勤務先
- その他
英語が苦手でも、審査官は対応に慣れており、ゆっくり話したり、簡単な表現で質問をしてくれることもあります。
ただし、これらの質問に対して「答えられない」「曖昧な回答をする」と、**別室送り(Secondary Inspection)**になってしまうリスクがあります。
別室送りになる理由と注意点
アメリカの入国審査では、以下の場合に別室送りになることが多いです:
- 質問に答えられない
- 回答が曖昧
- 書類不備や渡航目的の不明瞭さ
審査官は、入国させるべきか判断がつかない場合、別室送りを選択します。
とはいえ、ベテラン別室送り経験者の私としては「審査官の機嫌次第」とも感じます(笑)。
例えば、明らかに別室送り率が高い審査官を見たことがあります。3~4割の人を別室送りにしているような審査官も…。そして、不運にもその審査官に当たってしまうことが、人生というものですよね(笑)。
駐在員で別室送り経験者の割合とは?
アメリカ駐在員ともなると、アメリカへの入国審査も相当経験があります。
そんな駐在員で別室送りを経験した人はどれくらいいるのか?
私の周りの駐在員12人に聞いたところ、なんと4人が別室送りを経験していました。
 ライオンさん
ライオンさん33%!
割と簡単に「別室送り」になります。つまり、あなたが「別室送り」になる可能性も、十分あります!
最も厳しい空港はサンフランシスコ国際空港

 カバさん
カバさんどの空港が一番、厳しいの?
 ライオンさん
ライオンさんSFOでしょ!
アメリカで一番入国審査が厳しく、別室送りになる可能性が高い空港は「サンフランシスコ国際空港(SFO)」です。
あくまで個人的な経験に基づくものですが、私は3回中3回がサンフランシスコで別室送りになっています。もちろん、同僚の中にはシアトルで別室送りになった人もいますが。
私はサンフランシスコと、ただただ相性が悪いのか…
サンフランシスコでの入国審査の様子
それでは、私が1回目の別室送りになった際の入国審査の生々しいやり取りをご覧ください。
長いフライトを終え、ようやくサンフランシスコ国際空港到着。これまでの人生で一度も「別室送り」の経験もないため、余裕で入国審査に向かう。
そして入国審査官と対峙。
 ワシさん
ワシさんHello
 ライオンさん
ライオンさんHello!
 ワシさん
ワシさんアメリカには何しに来たんだ?
 ライオンさん
ライオンさん仕事で来たぜ!E-2ビザだ。
数年滞在すると思うぜ!
 ワシさん
ワシさんそうか、会社名は?
 ライオンさん
ライオンさんXXX株式会社だ!
 ワシさん
ワシさん名刺を見せろ
 ライオンさん
ライオンさんこのビザでは初めての入国だ。まだ名刺は無いぜ!
 ワシさん
ワシさん別室行きだー!
 ライオンさん
ライオンさんなんでだー!
ビザ書類も見せ、回答も明確にしてたつもりですが…名刺がないだけで「別室送り」。
ちょうど大統領選挙の真っ最中で、厳しかったのか…、素振りが怪しかったのか…、審査官の機嫌が悪かったのか…。
ただ、「別室送り」が宣告されてしまっては、どうする事もできません。抵抗しても事態が悪化するだけでしょうから、素直に別室に行きました。
ちなみに、何度も別室を経験しましたが、審査官は別室送りにした理由は教えてくれません。非常にモヤモヤした不安な気持ちで別室に行く事になります。
 ライオンさん
ライオンさんめっちゃ、不安…
恐怖の別室送りの実態

続いて、恐怖の別室の様子をお伝えします。*上の写真はSFOの別室に繋がるドアの写真:本物です(笑)
別室では入国するために追加で質問を受ける事になりますが、通常の入国審査の場所とは異なり、対応できるスタッフが少ないので長時間待つことになります。
それでは、緊迫した別室の様子をご覧ください。
私が恐る恐る別室に入ると、同じように別室送りにされた人々が多数座っていました。意外と多くの人がいて、なんか安心。
 ライオンさん
ライオンさん同じだ~
別室は厳しく、写真を撮る事は禁止。そして、携帯電話の使用も禁止。
私はサンフランシスコ入国、乗り継ぎでポートランドに向かう予定が、この段階でサンフランシスコ→ポートランドへの乗り継ぎまで、あと2時間。
 ライオンさん
ライオンさんこれ、乗り継げるのかな?
会社に連絡しようにも、携帯電話の使用を禁じられており、どうする事もできない。
「優先的に審査してくれないかな?」と席を立って審査官と交渉しようかと思った矢先、同じように乗り継ぎが迫った人が、審査官に問い合わせる。
 ウシさん
ウシさん乗り継ぎ時間が迫ってるんだ。先に対応してもらえないか?
 カバさん
カバさんお前、なんで入国できる気になってんの?
つまり、「お前は入国できるかどうかも分からないのに、なにアメリカ国内線の話してんの?黙って待ってろ」という事です。
 ライオンさん
ライオンさん怖すぎる!
この時点で、私は乗り継ぎを気にするのをやめ、第一目標を「入国」に切り替え!
ポートランドの空港に予約してあるタクシーのキャンセル連絡もできない状況ですが、もうどうしようもない。
 ライオンさん
ライオンさんすまん、タクシー運転手!
そして、待つこと、1時間半。
ようやく、私の番が訪れ、何を聞かれるのかと思いきや、ビザの書類を確認され、会社名を伝える等、入国審査と同じ内容。
同じことを回答したら、難なく突破。
 ライオンさん
ライオンさんなんで別室送りになったんだ…
他の別室送りになった人も、時間をかけて、しっかり確認されるものの、最後は突破していましたので、別室送りになっても恐れる事はありません。
乗り継ぎには失敗した
サンフランシスコからポートランドへのフライトには、結局、間に合わず。別室を突破した時点で残り15分でしたが、さすがに手遅れ。
 ライオンさん
ライオンさんダメか―
航空会社のカウンターに行き、事情を説明したら、数時間後の別便を手配してくれました。キャンセル代や追加費用は発生せず。
2回目・3回目の別室送り体験談
1回目の別室送りも意味不明でしたが、何と2回目・3回目は更に理由がわからないまま別室送りになりました。
と、言うのも、入国審査では「どんな仕事してるの?」に回答しただけで、ほぼ何も聞かれず。その後、なにやら長い間、ビザ資料をチェックして、コンピューターに何かを打ち込み、ビザ書類とパスポートを手に取ったかと思うと…
 ワシさん
ワシさん別室へ行け!
 ライオンさん
ライオンさんなんでだー!
完全に意味不明の別室送り。
そして、別室では更に意味不明の、何の質問も受けず、書類だけ確認されて解放。
 ライオンさん
ライオンさんなんで別室に送ったんだよ…
でも、二回目からは、慣れているのか別室に送られても全くビビらないですよ(笑)
別室送りを回避するための対策と備え
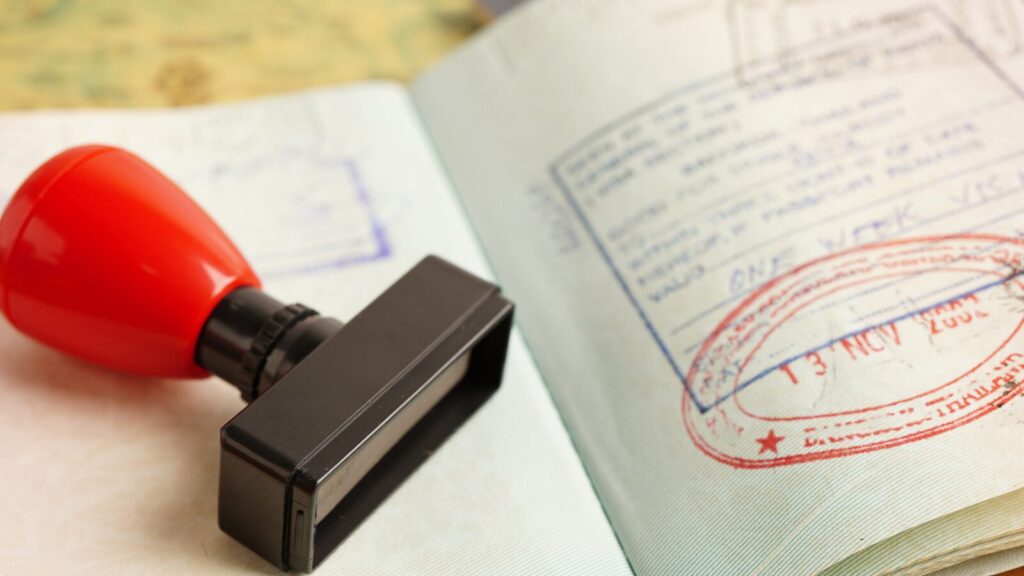
私の2回目・3回目の別室送りのように、全く意味不明の別室送りもあるので、「別室送り」になるかどうかは、審査官による部分、そして運の要素があるのも確か。
しかし、「別室送り」になると大幅にその後のスケジュールに影響を及ぼす可能性もあり、できるだけ対策はしていきましょう。
準備すべき書類と心構え
まず、出張や旅行でアメリカに入国する場合、予想される質問に対する回答をしっかり用意しておけば、別室送りになる可能性は極めて低いと思います。
改めて入国で聞かれる可能性のある質問は以下の通り。
- 滞在目的
- 滞在先、期間
- 持ち込む現金、食品など
一方、アメリカに住む人(ビザ)に対しては、旅行者より多くの細かい質問が投げかけられます。
これが曲者で、ビザ書類に書いてある内容と相違ない回答をしなければいけません。もちろん、ビザ内容に逸脱しているような事はしていないでしょうが、何年も前に書いたビザ内容なんて正確には覚えてない(笑)。
あと、ビザ取得時から昇進したりして役職が変わっていたりする事もあります。それは、全く問題ないのですが、ちゃんと審査官に説明しましょう(じゃないと別室送り)。
また、ビザによりますが、入国時に必ず見せないといけない書類もあります(私だとI-129など)。同僚が書類を携帯し忘れて入国審査に臨んだところ、お約束の別室送りになりました(最終的に入国はできた)。
- 住所
- 勤務先、職場での役職
- 仕事内容
- 滞在期間
別室送りへの備え
私の事例のように、どんなに備えていても不運で「別室送り」になる事はあります。そして、あまりに頻繁に別室送りを経験した私は、「入国空港での乗り継ぎは3時間以上あける」ようにしています。
もちろん時には3時間未満のフライトしかない事もありますが、もう別室送りを前提とした行動を取っている(笑)。
まとめ
今回はアメリカの入国審査で「別室送り」になった実話でした。
私の経験からすると、「別室送り」になっても、きっちり説明すれば突破できます。「別室?かかってこいや!」くらいの強気な気持ちで入国審査に臨んでください。
では、また。



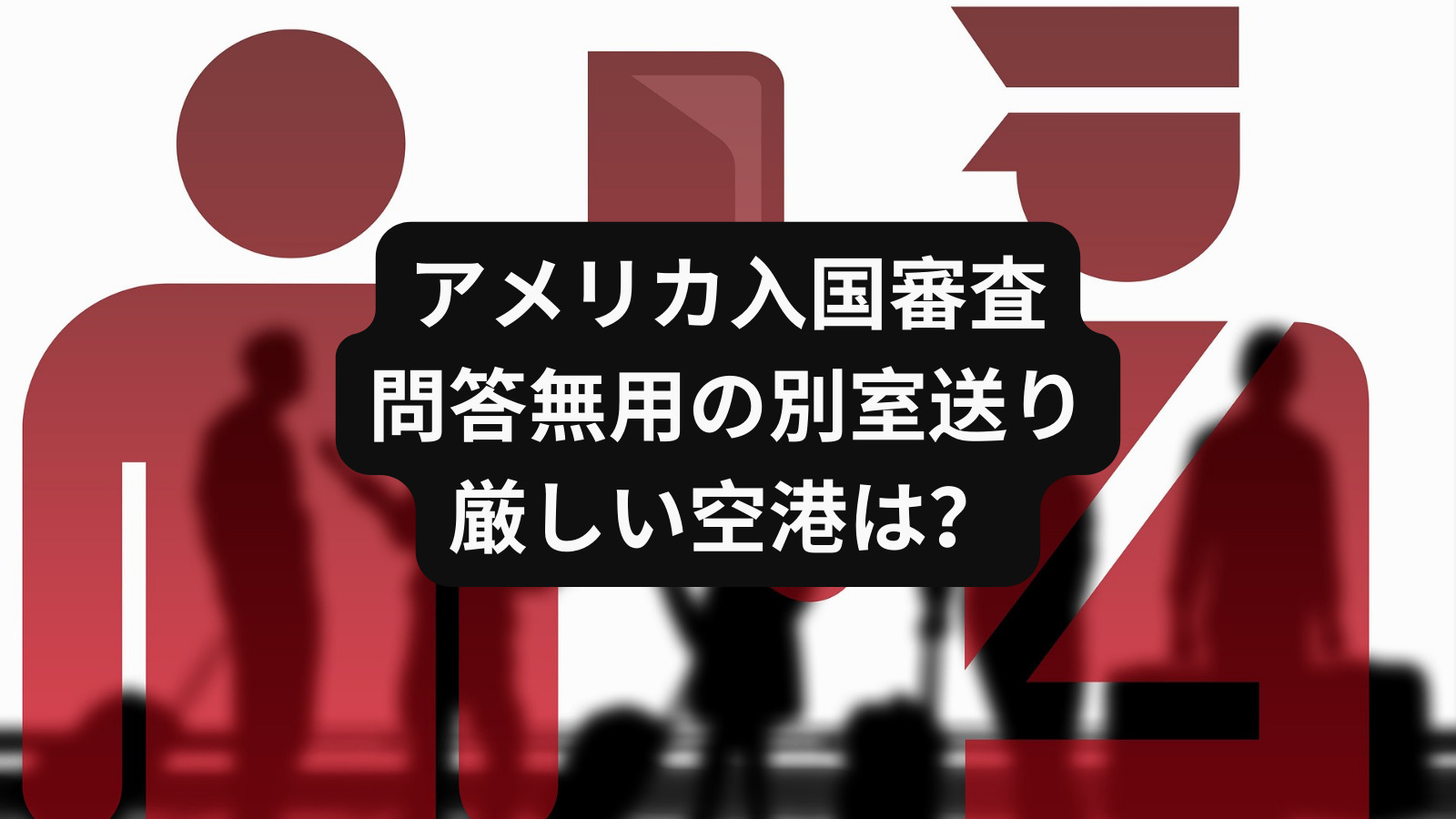
コメント