こんにちは、みみたまボーイです。
海外駐在員になって、はや9年。
いつの間にか人生の20%を海外で過ごしてしまっています。
海外駐在員をしていると、時折、「昔から海外志向だったんですか?」、「どうやったら海外駐在員になれるんですか?」と聞かれる事があります。
 ライオンさん
ライオンさんいや、知らねーし
と、昔は思っていたのですが、最近、駐在員を選ぶ立場にもなってきて思うんです。
 ライオンさん
ライオンさん海外赴任に選ばれる確率を高める方法はある
私自身は特別な海外志向はなく、いつの間にか海外赴任を言い渡されてしまったので、なぜ私が駐在員に選ばれたのか明確な理由は不明です。
ただ、今、振り返ってみると、私は知らず知らずに駐在員に選ばれやすそうな行動を取っており、恐らくそれが駐在員に選ばれる一因になっていた…と、選ぶ側になって感じます。
そんなわけで、今回は、「どういう人が海外駐在員に選ばれやすいのか」を、私の実体験&選ぶ側に回ってわかる視点からまとめてみました。
「何とか海外赴任したい!」、「駐在員になりたい!」と思っているあなたの参考になれば嬉しいです。
では、いってみましょう。
海外赴任に選ばれる人の5つの特徴
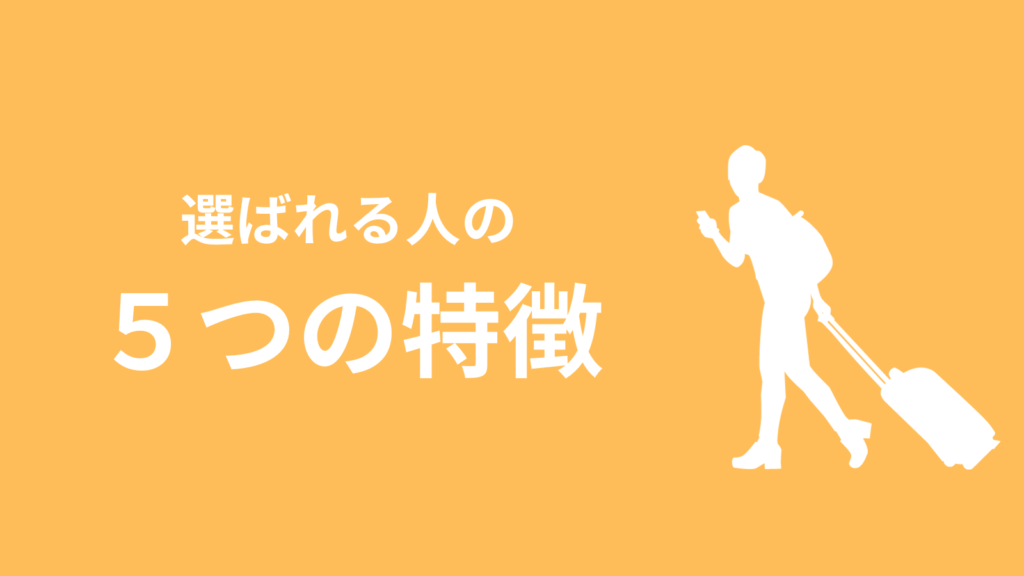
さっそく、海外赴任に選ばれる人の特徴を5つ書いてしましましょう。
駐在員に選ばれるために重要な順番で書いてみました。
- 海外赴任したい意思を明確に発信している
- 健康である
- チャレンジ精神
- そこそこ仕事ができる
- 英語が得意である
海外赴任したい意思を明確に発信している
「え、そんな事?」と思うかもしれませんが、これはとてつもなく重要です。
 ライオンさん
ライオンさん決定要因の5割以上はこれかも
もしあなたが駐在員になりたいと思っているなら、周囲に明確に「海外赴任したい!」と発信しましょう。
上司との面接の時でもいいですし、職場でもいい、飲み会でもいい。
とにかく、「自分は海外赴任したい!」、「海外赴任に何の抵抗もありません!」というのを発信し続けてください。
これだけであなたが海外赴任に選ばれる確率が2~3倍は上がります。
 カバさん
カバさんでも、なんで?
そんな疑問が聞こえてきそうですが、じつは海外赴任を打診してスンナリ受ける人って、それほどいません。
国内で転勤になるのとは違って、環境の変化が非常に大きいですからね。
家族の負担なども考えて、海外赴任を躊躇する人も多いのが現実。
しかし、選ぶ側からすると、「誰かには行ってもらわないといけない…」という切実な悩みがあります。
そんな時、普段から「海外赴任したい!」と明確に宣言している人がいれば、上司は間違いなく候補として考えます。
 ライオンさん
ライオンさん断られない安心感
もちろん、「海外赴任したい!」と言ってても、行けない事もあります。
海外事務所に唯一の日本人を送るケースなど、求められるスキルを含め、条件が合わないと選ぶわけにもいきません。
しかし、こんなことを言っていいのか分かりませんが、じつは「とりあえず、誰でもいいから派遣しろ」というケースもあります。
 ライオンさん
ライオンさん割と多い…
こんな時、まず誰に声を掛けるか考えてみてください。
 カバさん
カバさん行きたがってるやつだな
 ライオンさん
ライオンさん正解
誰でもいいんだったら、普通、行きたがってる人から声を掛けます。
断られるリスクもありませんし、何より、海外で働く意思の強い人に行ってほしいですからね。
そんなわけで、海外駐在員になる可能性を最も高める方法は「駐在員になりたい」と明確に周囲に発信する事なのは間違いありません。
健康である
「健康」も非常に重要なポイント。
ここでいう「健康」はメンタル、及び身体的な健康の両方を指しています。
まず、メンタルですが、海外駐在生活は慣れてしまえばどうって事は無いのですが、赴任初期は極限までストレスが溜まるものです。
言葉は通じないし、食べ物は違うし、友達もいない。
更に、駐在員は日本でいた時より、職責も上がり、これまでより多くの仕事(量、領域)をカバーする事になります。
そんな環境にも関わらず、言葉の問題もあり、本来持ちうる力の30%くらいしか発揮できず…自己嫌悪に陥る事、間違いなし(笑)。
私も赴任初期の3カ月ほどは無力感に苛まれ、精神的に結構ヤバい状態までいきましたね(笑)。
連休も何もする気が起きず、家でひたすら寝続ける…
 ライオンさん
ライオンさん確実に病んでた(笑)
また、日本と現地の板挟みになる事も多々あり。
そんな過酷な海外ストレス環境に耐えれるような「鋼のメンタル」を持っているかは上司は確実に見ています。
派遣した人が1年も経たずに途中帰任になっては意味がありませんし、そもそも海外赴任する人にメンタル不調になって欲しくありません。
そんなわけで、良いのか悪いのか、ソコソコのストレス耐性が必要。
次に「身体的な健康」も重要な要因になります。
と、言うのも、ひとつの海外事務所に大量の日本人を派遣できるような余裕のある会社は少なく、多くの場合、少数の駐在員で海外サイトを回していく事になります。
つまり、調子が悪かろうが、代わりはいない。
日本だとちょっと風邪をひいて休んでも、同僚がカバーしてくれたりという事が可能です。
ただ、海外はそういはいきません。
風邪だろうが、何だろうが、物理的にあなたしかいない(笑)。
 ライオンさん
ライオンさんあなたが止まると、全ての仕事が滞る
そんなわけで、日本にいる時から頻繁に風邪をひいている人とかは選びにくい。
もちろん、わざと風邪をひく人はおらず、体質なのでしょうがないのですが、ただでさえ少数の海外サイトに送る人としては選びにくい…というのが正直なところ。
ちなみに、私は日本にいる時は毎日晩酌していたのですが、海外赴任になり「代わりがいない(本当に一人しかいなかった)」状況にビビり、禁酒しました。
 ライオンさん
ライオンさん健康になって良かった
チャレンジ精神
チャレンジ精神も重要です。
海外サイトに派遣されると、言葉の問題を抱えながらも、現地社員との信頼関係を築いていかなければいけません。
拙い英語だろうが何だろうが、仕事をするためには話しかけなければいけません。
全く通じず、「はぁ?」と3回繰り返されようが、諦めずに伝えきる精神力。
「くそー、今日も全然伝わらなかったな!」と、凹んでも次の日には立ち上がってこれる不屈のチャレンジ精神を持っているか、ある意味では「鈍感力」が必要です。
また、少数で回している海外サイトにおいては、これまで自分がこなしてきた仕事の分野とは全く異なる仕事を任される事もあります。
私も、工場で生産現場を任されていたのに、「人がいないから…」という理由で、馴染みも全くないような「売り上げ見込み」を作らされたことがあります。
 ライオンさん
ライオンさんやったことねーし
全くわけもわからないまま、周りに聞いて徹夜して、何とか仕上げた記憶があります。
そんな風に、全く馴染みの無い仕事が降ってきたりもするものの、「やってみなはれ」の精神でチャレンジしていける人が海外駐在員には向いています。
そこそこ仕事ができる
仕事が全くできないと、さすがに少数で回す海外サイトに駐在員として派遣される可能性は減ります。
特に部下を持つような立場で派遣される場合、基礎となる仕事のスキルがしっかりしていないと現地社員からの信頼も得られませんし、最悪、現地社員から舐められてしまうと海外サイトそのものが終わりです。
会社によっては「教育」を目的に派遣する事もあるので、スキル不十分の状態での海外赴任の可能性もあるのですが、教育派遣の場合も将来嘱望されている人を出すことが多いので、全然仕事ができないと望み薄。
例外は、「誰でもいいから派遣しろ!」というケースで、「よくこのスキルで…」という人が、派遣される事もあります。
私の部下にも「スキルもまだまだ不十分」、「英語も喋れず」という状態で派遣されてきた人もいました。
 ライオンさん
ライオンさん途中帰任しちゃったけど…
英語が得意である
英語は喋れるに越したことはありません。
 ライオンさん
ライオンさんしかし、必須では無い
じつは選ぶ側からすると、赴任時の英語力は、それほど重要視していなかったりします。
それよりも上で書いた「仕事のスキル」の方が何十倍も重要な要素です。
と、言うのも、赴任時に英語を喋れなくても、ソコソコ仕事ができる人は赴任してからの努力で、多くの場合、ソコソコ喋れるようになります。
それに、平均的な日本人より英語が少し喋れるくらいでは、アメリカをはじめとするネイティブ環境では全く歯が立たず、結局、赴任後の英語の強化は必須。
もっと言うと、選ぶ側の多くの人は、海外駐在を経験しているので、その辺を自ら経験から理解しており、「言語は何とかなるだろ」と思っているところがあります(笑)。
 カバさん
カバさん勝手な思い込みだな(笑)
 ライオンさん
ライオンさん何とかなっちゃったからね(笑)
もちろん、中には留学経験があるなど英語ペラペラ人材もいるでしょうが、まだまだ日本には少ないでしょう。
とはいえ、英語を勉強しないでいいと言っているわけではありません。
 ライオンさん
ライオンさん勘違いするな
海外生活においては英語は必須。
私はこれまでアメリカ、台湾と経験していますが、どちらの国でも最低限の英語力は必要です。
あくまで駐在員を選ぶ時に、そこまで重視されてないだけで、駐在生活に英語は欠かせません。
多くの駐在員は赴任後半年くらいは自分の英語力の無さに毎日凹みながらも、血反吐を吐いて英語を勉強する事になります(笑)。
 ライオンさん
ライオンさんまじで辛い日々
ちなみに、非常に稀な例ですが、私の部下に赴任後も英語が全く伸びず、現地社員とも上手く関係を築けず、残念ながら途中帰任となってしまった人もいます。
そんなわけで、海外駐在員になるなら英語の勉強はしておいて損はありませんし、「いつか喋れる」と甘く見過ぎてはいけません。
 ライオンさん
ライオンさん努力しないと全然伸びず、途中帰任…
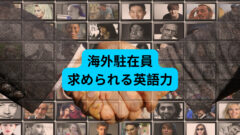
私が海外赴任に選ばれた理由(推測)

海外赴任に選ばれる5条件を出したところで、私が選ばれた理由を推測してみます。
5条件の内、私が選ばれた理由は、おそらく主に「健康である」、「英語が得意」の2点。
それに加え、海外赴任を希望していたわけでは無いものの「海外もアリかな」という会話を上司としていた事が、海外赴任要員となった理由だと推測しています。
健康である
私、体だけは丈夫で、風邪とか殆ど引いたことがありません。
学生時代も風邪で休んだ事とかないですね。
メンタル面は、「鋼のメンタル」とは思いませんが、思い悩んだりはしないタイプと言うか、どっかで開き直って対応できるので、その辺も見られていたんでしょう。
 カバさん
カバさん適当な性格だよね
 ライオンさん
ライオンさんほっといてー
まあ、そんな私でも駐在生活の中では極度のストレスにより、蕁麻疹が出たりしましたが(笑)。
英語が得意だった(?)
私が入社した頃って、今とは比べ物にならないほど、平均的な日本人の英語力が低かったんです。
入社時の私のTOEICの点数が650点くらいだった気がします。
今だったら800点とか900点とかザラにいますが、当時は650点でも高かった(笑)。
650点なんて、実際には何の役にも立たない英語力ですが、相対評価で「英語が得意な人」というカテゴリーに入れられてしまったわけです。
当時は、上司にも英語を喋れる人は殆どおらず、おのずと英語で対応しないといけないような仕事が私に振られてきました。
 ライオンさん
ライオンさん全然喋れないのに…
そんな中、上司との業務面接の中で「将来的に海外サイトとかもアリなの?」と言われ、「うーん、まあアリっすね」と回答していたら、数年後に海外赴任の打診を受けた。
そんな感じです。
健康かどうかは持って生まれた部分があるのでどうしようもないかもしれませんが、海外に行きたいと発信する事は誰でもできますし、英語力は選ばれる確率を上げるには役立つでしょう。
海外駐在員を選ぶプロセスを公開
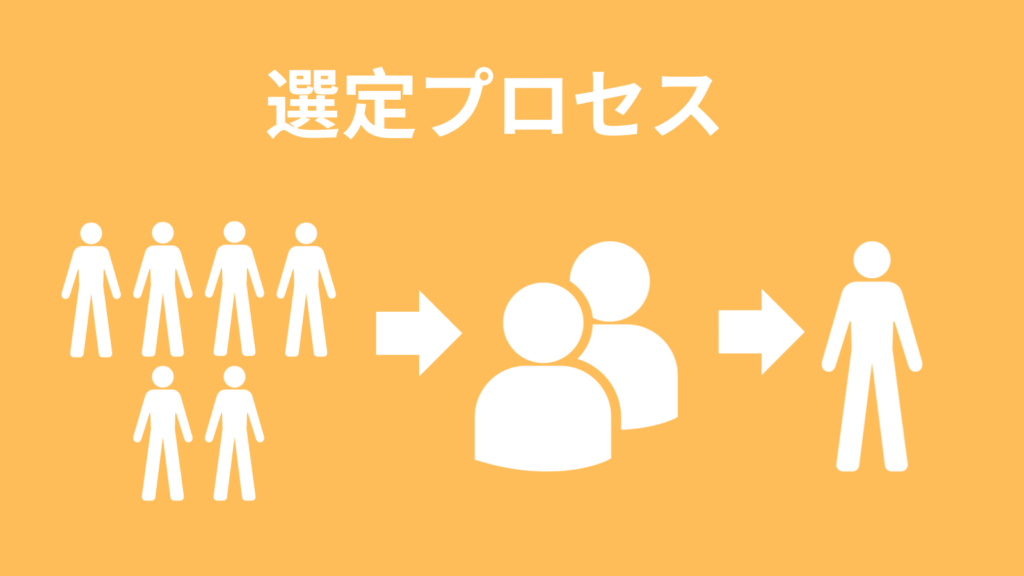
ここでは、実際に私が駐在員候補者を選定し、海外赴任を打診したプロセスを公開しましょう。
私が台湾駐在を終える際の、後任選びで実際に行ったプロセスです。
- 海外赴任候補者を複数人選ぶ
- 現役駐在員の意見を反映させて選定
- 本人に打診
海外赴任候補者を複数人選ぶ
海外駐在員を選ぶ際は、特定の個人を一本釣りするか、海外赴任に適していそうな候補者を複数選び、そこから絞り込んでいくかのどちらかです。
一本釣りのケースも結構ありますが、私の経験だと6~7割は複数人から絞り込んでいくプロセス。
現在駐在している人の帰任期限の2年前くらいから、後任選定プロセスが開始されます。
 カバさん
カバさんえ、かなり早いな
そうなんです。
海外駐在員の候補者選びというのは、じつはかなり早くから選ぶ人の間では議論されています。
私が台湾駐在の後任を選ぶ際は、日本側で3名の海外赴任候補者を選び、私も2名候補者を選んで打ち合わせを重ねて絞り込むスタイル。
海外赴任を言い渡される側は「急だな!」と感じる事が多いのですが、選ぶ側はかなり前から準備しています。
普段の会話の中で、さりげなく海外赴任の意向を聞いてみたりしているので、注意深く上司との会話を解析すると面白いかもしれません。
 ライオンさん
ライオンさん絶対ほのめかしてる(笑)
現役駐在員の意見を反映させて最終選定
赴任の1年くらい前には、最終選定までほぼ終わっています。
そして、海外赴任候補の最終選定で、割と大きなウェイトを占めるのが「現役駐在員の意見」。
 カバさん
カバさんどういうこと?
と、いうのも、日本側は現地の実情なんてわからないですからね。
リアルタイムで現地の仕事状況、生活環境を経験している現役駐在員の意見は無視するわけにはいきません。
つまり…現役駐在員と親しいと選ばれやすい(笑)。
出張で現地に赴いた時に「海外赴任したい」という情報を現役駐在員の耳に入れておくと、割と効果があったり…
もちろん、確実な方法ではなく、裏ワザ的なモノですが、やっておいて損なし。
本人に海外赴任を打診
会社の規定にもよるでしょうが、本人への海外赴任打診の時期は赴任の半年前~3カ月前が多いようです。
国内異動とは違い、ビザ申請などで時間がかかるので、比較的早く打診を受けるでしょう。
なお、海外赴任を拒否されるケースも考えて、選ぶ側は第3候補くらいまでは用意しているので、返事を長引かせるのは得策ではありません。
 ライオンさん
ライオンさんすぐ回答しましょう
なお、海外赴任決定後は、準備でやることが目白押しなので、業務そっちのけで海外赴任準備の準備をするのが◎。
こんなやつは来るな!失敗する駐在員の特徴
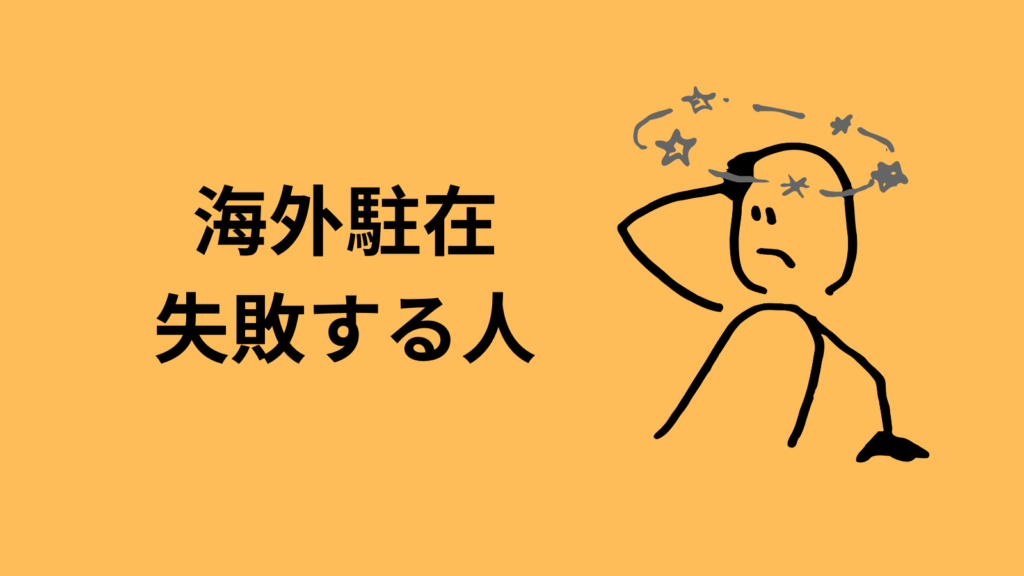
10年も駐在員をしていると、残念ながら海外生活に合わず途中帰任となる人も多く見る事になります。
そんなわけで、ここでは、失敗する駐在員の特徴を書いてみたいと思います。
- 異文化を受け入れれない
- 現地化しすぎる
- 言語が成長しない
- 真面目過ぎる
- 女好き
異文化を受け入れれない
アメリカ、台湾と駐在生活をしてきて、どの国も文化の違いはあり、これを受け入れていく度量が無いと失敗します。
例えば、アメリカはトップダウンではなく、部下からも積極的に意見が出てきます。
つまり、日本の感覚でトップダウンで指示を出すと、部下から「何でやるの?」、「こっちの方がいいんじゃない?」とガンガン質問される。
これに「まあ、とにかくやっといて」的な返しをすると、現地社員から総スカンを喰らいます(笑)。
もちろん、多くの駐在員は頭では異文化を受け入れないといけない事を理解していますが、実際、目の当たりにすると、意外と受け入れれない人もチラホラ。
 ライオンさん
ライオンさん1割くらいだけどね
現地化しすぎる
「異文化を受け入れれない」人も失敗しますが、現地化しすぎて失敗する人も一定数います。
海外への興味が大きすぎる人にありがちなのが、完全に現地に迎合してしまうパターン。
何でもかんでも現地の言っている事を受け入れると、日本の意向を現地に浸透させる役割を担う駐在員としては終わりです。
とはいえ、何でもかんでも日本に従えばいいかと言うとそうでも無く、そこのバランスを上手く取るのが駐在員の醍醐味。
 ライオンさん
ライオンさんつまり、ストレス原因(笑)
これを乗り切るための私のアドバイスは「常にフェアに判断する」。
異文化だ何だと、色々言われますが、アメリカだろうが台湾だろうが、結局動かしているのは「人」。
難しく考えずにフェアに何がベストかを考え、時に現地と闘い、時に日本と戦えばいいと思います。
そうしてフェアに対応すれば、「こいつは日本からの指示を伝えるだけじゃない」事が現地社員にも伝わり、自然と信頼関係も構築されます。
時には、渋々、日本の指示通りやらないといけないこともありますが、それはそれで、しっかりと日本と話した後に、現地にも率直に伝えれば、多くの場合理解されます。
言語が成長しない
言語が全く成長せずに途中帰任となる人はいます。
こんな理由で失敗するのは、とてももったいないので、あなたはこんな事態になってはいけません。
もちろん英語や現地言語を話せるようになるのは簡単な事ではありません。
でも、別にペラペラになる必要は無いんです。
英語なら半年本気でやれば、何とか業務をこなせるだけの言語力(英語や現地言語)は身に付くはずです。
 ライオンさん
ライオンさん何とか頑張って!
↓リアル途中帰任者の話はこちら↓
真面目過ぎる
真面目なのは良い事ですが、海外で真面目過ぎると、思い詰めて精神的に病んでしまうので注意が必要です。
もちろん、日本でも真面目過ぎて病む事はありますが、海外だと近くにいる日本人の数が絶対的に少ない=心の拠り所が少ないため、より一層病みやすい環境にあります。
それでいて、日本と現地の板挟みによる極度のストレス。
「自分ではどうしようもない、もうどーしたらいんだ…」と、一人で抱え込み、いつの間にか鬱症状。
 ライオンさん
ライオンさんマジであります
私も極限までストレスが溜まって蕁麻疹になった事がありますし、本人は意識してなくても、いつのまにか体が悲鳴を上げていた…というケースは多々あります。
性格の問題なので難しいのですが、私はどうしようも無くなったら「まあ、俺の会社じゃねーし、どーでもいいか」と開き直って、ストレスをリリースしています(笑)。
 ライオンさん
ライオンさんそうしないと精神やられる
人それぞれでしょうが、何かしら自分の気持ちを保つすべを確保しておいた方がいいですよ。
女好き
私生活で羽目を外し過ぎて失敗する人は、必ずいます。
特に、単身赴任の人にありがちなので、気を付けてください。
アメリカは、夜のお店がそれほどないのですが、台湾駐在時代には、給料の殆どをキャバクラ等につぎ込み、生活を破綻させて帰国していった人が…いっぱいいた(笑)。
お金が無くなるだけならまだしも、家庭も崩壊。
 ライオンさん
ライオンさん困ったもんだ
海外駐在員のリアルな仕事
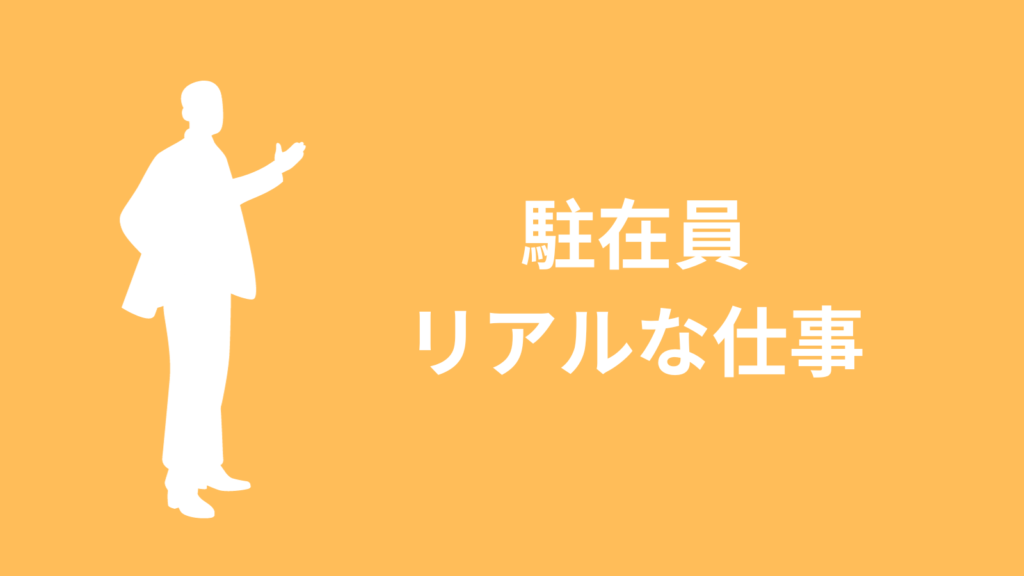
ここでは、海外駐在に興味をもっているあなたに、駐在員のリアルな生活を赤裸々にお伝えします。
駐在10年の私が言うので、間違いありません(笑)。
駐在員って、実際どんな仕事?
まず、駐在員の主な仕事は以下の3つ。
- 現地事務所の円滑な運営
- 日本と現地のブリッジ
- 出張者アテンド
現地事務所の円滑な運営
駐在員は日本から現地事務所を円滑に運営するための管理者として派遣されるケースが多いと思います。
現地法人のトップではなくとも、少なくとも日本から代表として送り込まれており、現地事務所の運営に大きな影響力がある立場。
日本の本社は現地の細かい状況を把握できるわけもなく、自分の判断でバシバシ決めて運営していく事になります。
ある意味では自由ですが、失敗したら自分の責任なので、それなりにプレッシャーも感じる。
特に日本から派遣された直後は、日本で受け持っていたより大きな職責に「これ、俺が決めちゃっていいのかな?」、「失敗したら…」と不安になる事も多々あります。
 ライオンさん
ライオンさんだんだん麻痺してくるけどね
日本と現地のブリッジ
現地法人の管理者としての立場での派遣の場合はもちろん、実務レベルでの派遣であっても、日本と現地のブリッジとしての役割は必ず求められます。
日系企業の場合、日本のノウハウを海外拠点に伝えていくスタイルが多いので、その役割を担う。
また、日本から「現地にXXを導入しろ」といった指示も来るので、それを現地で展開する役割。
駐在員の仕事の多くが、このブリッジ機能ですが、現地の事もロクにわかっていない本社からの指示に「現場の事もわからずに!」と思う事も多々あります(笑)。
いわゆる「OKY!(お前が来てやってみろ!)」ですね。
 ライオンさん
ライオンさんOKY!OKY!
これはマネジメントレベル、実務レベル関係なく感じるストレスだと思いますね。
出張者アテンド
「出張で来る人のお世話」も駐在員の役割です。
たまに、社長とか偉い人が来たりするので、移動の手配、ディナーの設定など、現地の手配をしないといけません。
 ライオンさん
ライオンさんめんどくせー(笑)
出張者のアテンドは面倒ではありますが、日本にいると話すことも無い人とガッツリと話す事ができるので、それはそれで楽しかったりします。
海外に来るとみんな口が軽くなるので、人事の話とか、秘密の話を聞けることも多々ありますね(笑)。
駐在員って楽しいの?
駐在員が楽しいかと言われると…
 ライオンさん
ライオンさんまあまあ、楽しい(笑)
もちろん、辛い事もあります。
時差もあって労働時間もあってないようなものだし、日本と現地の板挟みにあってストレス溜まりまくるし。
「やってらんねーよ!」と思う日もありますが、総合してみれば、駐在生活は悪いものではありません。
何より良いのが「自由」!
多少は日本から、あーしろ、こーしろと言われますが、自分の裁量で自由に判断して動けるところが多く、その分、責任はあるのですが、慣れてしまえば楽しいものです。
あと勤務時間も柔軟で「午後は子供を迎えにいくので、早めに帰る」といった事が、気軽にできて過ごしやすい。
代わりに、やらないといけない時は早朝、深夜まで働きますが、自分の好きな時間に集中してできるので、それほど辛くは無い。
↓駐在員のメリット・デメリットはこちら↓

駐在員になるべきなのか?
海外駐在に興味がある人に、駐在経験10年の私が海外駐在を薦めるかと言うと…
 ライオンさん
ライオンさん薦める!
生まれ育った日本を離れ、海外で生活するので、興味と不安が入り混じるのは当然です。
でも、住んでしまえば、意外とイケるものです。
台湾、アメリカ(2回)と全然違う環境にたらい回しにされ、どっちにもすぐに慣れた私が言うので間違いありません(笑)。
海外生活に慣れてくると、日本から解き放たれすぎて、むしろキッチリしている日本には帰りたくなくなりますよ。
 ライオンさん
ライオンさんたまに帰るくらいが丁度いい
それに、これまでとは違ったアングルで外から日本を見る事で視野が広がり、仕事上のキャリアに留まらず、あなたの人生全体にとってプラスになる事、間違いなし。
興味があるなら、ぜひ一歩踏み出してみてください。
まとめ
今回は海外駐在員に実際に選ばれ、そして選ぶ立場になった私の視点から、海外駐在員になるための5つの特徴について書いてみました。
5つ書いてみましたが、海外赴任に選ばれるのに何より大事なのは「なりたい」という自らの意思を明確に示し続ける事です。
これだけであなたが駐在員になれる可能性は飛躍的に高くなる事間違いなし。
仕事で必要な基礎スキルを高めつつ、赴任後に必須となる英語の勉強も進めていってください。
では、また。


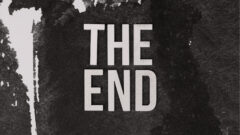
コメント