こんにちは、みみたまボーイです。
海外駐在生活も気づけば10年。初赴任時は小さかった娘も、いまや中学生になりました。日本の小学校に通ったのはほんのわずかで、ほとんどを海外で過ごした彼女。
そんな我が家で、いよいよ現実味を帯びてきたのが「帰国子女の進路」の話です。
幼稚園や小学校の頃は「まぁ何とかなるだろう」と楽観的に構えていましたが、中学ともなると高校受験が視野に入り、一気に現実味が増してきます。
我が家の場合、私の本帰国のタイミングは未定。でも、娘はアメリカの高校に進学するつもりはなく、日本の高校への進学を希望。
とはいえ、「Middle School(中学)」は最後まで通いたいようで、帰国時期は中学2年生の夏休み前後になりそう。そこから受験勉強…
 ライオンさん
ライオンさん間に合うのか?
そこで今回は、帰国子女が選べる進路や、高校受験・編入・帰国子女枠などの具体的な選択肢について、調べたことをまとめました。
同じように、お子さんの進路について悩んでいるご家庭の参考になればうれしいです。
では、早速いってみましょう!
帰国子女の進路選択とは?基礎知識を押さえよう
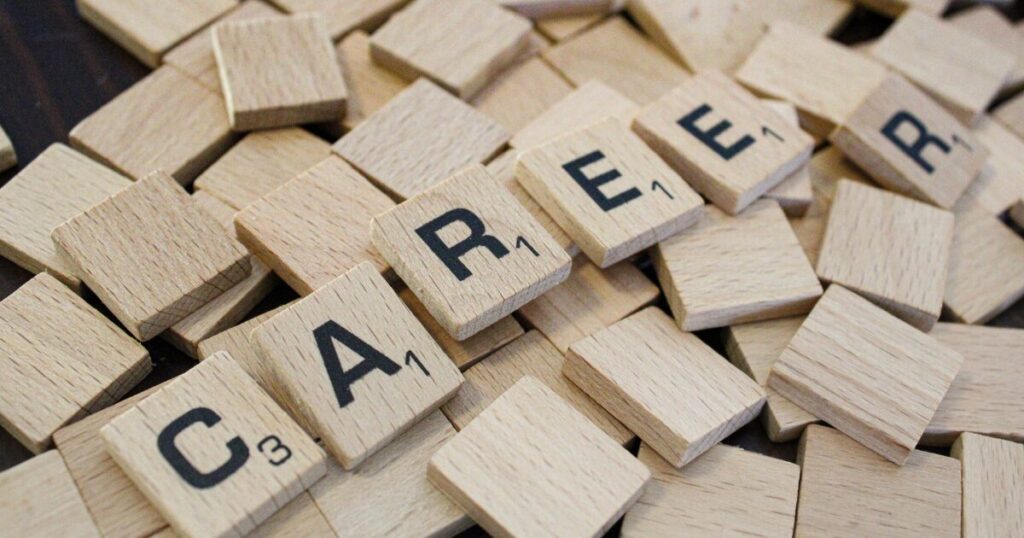
帰国子女として日本に戻るとき、どんな進路を選べるのか。
まずは、帰国時に直面しやすい課題や、高校受験・大学進学を見据えた進路の選択肢について、基本的なポイントを押さえておきましょう。
帰国子女が直面しやすい3つの課題とは?
実際に我が家でも感じていることですが、帰国子女の進路に立ちはだかる壁は少なくありません。代表的な課題は、以下の3つ。
- 日本の教育システムとの違い
- 帰国時期による進路への影響
- 学力のギャップと高校受験の難しさ
日本の教育システムとの違い
アメリカの学校は自由でのびのびしていて、個性を尊重する雰囲気があります。失敗を恐れず、自分の意見を言える力が育つのは大きな魅力。
一方、集団行動を重んじ、ルールに厳格。テスト重視のカリキュラム。
 ライオンさん
ライオンさんそれは、それでよい面もあるが
このギャップに、我が子はうまく馴染めるのか…一抹の不安を抱かないわけではありません。
帰国時期による進路への影響
いつ日本に帰国するかで、進路は大きく変わってきます。
例えば、中学校や高校の入学タイミングで帰国できればスムーズですが、実際は親の仕事の都合などでそう簡単にはいきません。
また、我が家のように娘から「Middle Schoolは卒業したい」という希望が出ることも。娘の意思は尊重したいものの、日本の高校受験への準備期間短くなり、悩ましい。
子供の気持ちと将来をどう両立させるか。
正解はないからこそ、将来の進路まで含めた長期計画を娘と話し合い、子供も納得した形での結論を出していくことが大切だと感じています。
学力のギャップと受験の難しさ
アメリカの現地校に通っていると、日本の教科に触れる機会は限られます。
私が暮らすオレゴン州にも週末の補習校はありますが、日本の学校のように毎日授業を受けられるわけではありません。
そのため、特に「社会(地理・歴史)」や「理科」の知識はかなり不安…。うちの子なんて、日本の都道府県すら怪しいレベル(笑)。
このように日本で教育を受けている同年代の子供とは間違いなく学力ギャップがあるなかで、どのようにして高校受験、その先の大学受験を乗り切っていくのか。
 ライオンさん
ライオンさんこれが一番悩ましい
帰国子女の進路選択肢とは?
帰国子女にとって、日本での進学は悩みのタネになりがちです。
海外とは異なる教育制度や受験の仕組みに戸惑うことも多く、「どんな進路が選べるのか?」と情報収集を始めるご家庭も多いのではないでしょうか。
ここでは、実際に検討されることの多い「帰国子女の4つの進路オプション」について、それぞれの特徴とメリット・注意点をわかりやすく解説していきます。
- 帰国子女枠を活用した高校受験
- インターナショナルスクールという選択肢
- 一般入試での高校受験
- 編入試験を利用する方法
帰国子女枠を活用した高校受験
高校受験まで時間が少ない場合、一番現実的な選択肢なのが「帰国子女枠を利用した高校受験」だと思います。
この制度は、高校によって条件が異なりますが、一般的には「帰国後3年以内」などの要件を満たせば出願可能。試験科目も英語・数学・国語などに限定されていることが多く、我が子のように社会・理科に不安がある子供にはお薦めかもしれません(笑)。
インターナショナルスクールという選択肢
あえて、日本でインターナショナルスクールに入り、そこから大学進学を目指す道もあります。
この道を選べば、これまでの海外生活で培った英語力や教育スタイルが活かせるため、子どもにとっては「環境のギャップ」が少なく、精神的な負担も軽減されるかもしれません。
費用が高額で悩ましいのと、日本の大学受験を受験するつもりだと、それに向けた準備に特化していないのが、やや難点でしょうか。
一般入試での高校受験
いわゆる「普通の高校受験」も、もちろん選択肢のひとつです。
ただし、これは他の日本人中学生と同じ条件で挑むということ。海外で育った帰国子女にとっては、学習内容の違いや言語の壁が立ちはだかることもあり、本人の努力と覚悟がかなり求められるチャレンジになります。
 ライオンさん
ライオンさんやる気と根性!
ただ、うちの場合、中学2年の夏に日本に帰ってからだと、物理的にキャッチアップする時間が足りないんじゃないかと懸念しますね。
編入試験を利用する方法
海外で高校に入学したあと、日本の高校へ途中から「編入」するという選択もあります。
編入試験の多くは国語・数学・英語など、基礎科目のみで構成されており、一般入試に比べると準備のハードルがやや低めと言われています。帰国時期によっては、最もフィットする進路になるかもしれません。
ただし、編入を受け入れている高校は限られており、そもそも募集人数が少ないため競争率が高くなることも。希望する学校への編入を成功させるためには、早めの情報収集と戦略的な準備が不可欠です。
帰国子女枠の活用方法とそのメリット
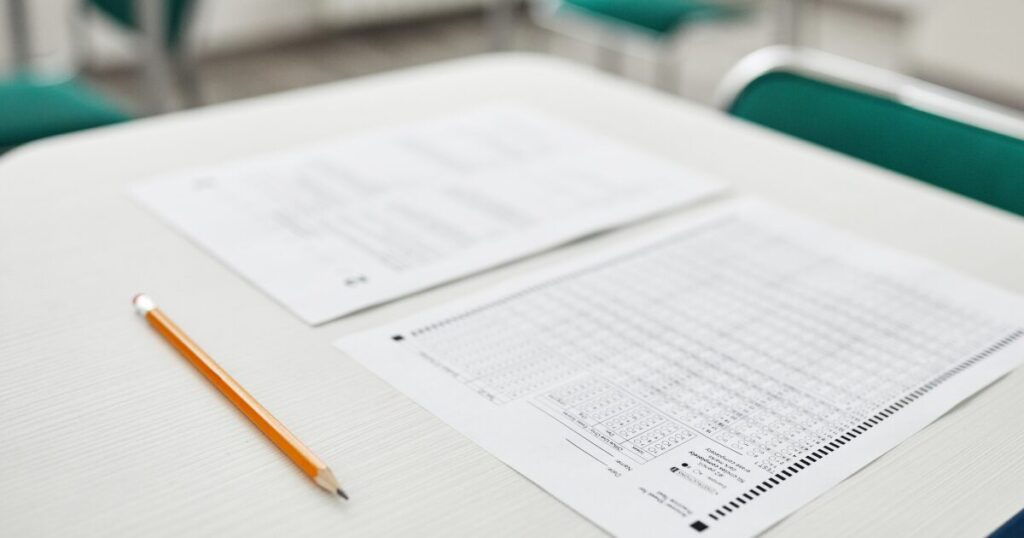
我が家における現実解に近そうな、帰国子女枠での高校入試について、詳細を調べてみました。
一般的な帰国子女枠の要件
帰国子女枠を利用して高校入試を受ける場合、各学校によって条件は異なりますが、一般的に以下の要件が求められます。
- 帰国後の経過年数:多くの場合「3年以内」
- 海外在住期間:多くの場合「1年以上」
- 受験科目:国語・数学・英語の学力試験が一般的。特に英語は重要視され、リスニングやエッセイライティングを含む場合もあり。面接を実施する高校も多い。
- 保護者との海外滞在条件:「保護者とともに海外に滞在していたこと」が受験資格の一つに含まれる。
- その他の要件:英語資格(TOEFL・IELTSなど)の提出を求める場合や、海外の成績証明書の提出が必要になることもある。
帰国子女枠で入学できる高校の特徴
帰国子女枠を設けている高校は、主に国際科や英語教育に力を入れている学校が多い傾向があります。
国際科・国際教養科が多い理由
帰国子女枠のある高校には、国際科・国際教養科・英語科などを設置している学校が多くあります。これは、帰国子女が持つ語学力や海外での学習スタイルを活かせるようなカリキュラムを提供するためで、
- 英語教育が充実(ネイティブ講師による授業、英語でのディスカッション)
- 国際的なカリキュラムを採用(IBディプロマプログラム、海外大学進学向けプログラム)
- 留学制度や海外交流が盛ん(交換留学や海外研修が充実)
といった、特徴があります。
普通科への進学も可能
国際科や英語科と比較すると少ないものの、帰国子女枠で入れる普通科もあります。
国際科や英語科では、数学・理科の授業時間が少なめになる場合があるため、将来理系の大学進学を考えている場合は、普通科を選ぶことで受験科目の準備がしやすくなるメリットあり。
当然、理系に興味のある帰国子女もいますからね。
もちろん、国際科や英語科に入ったからといって、文系に進まないといけないわけではなく、自力で理系科目の力を延ばせば、国際科や英語科から工学部などへの道もあります。
帰国子女枠の試験内容と対策
帰国子女枠で高校入試となった場合、帰国後は、とにかく国語、数学に集中かと思います。
英語は、文法問題や英作文の形式、長文読解の出題パターンなど、「読み書き中心」の日本式英語への対応がポイントかなと。
国語・数学の対策
最優先で取り組むべき「国語」と「数学」。
帰国子女枠の試験内容は、学校によってバラつきがあるものの、多くの場合は日本の中学教科書レベルの内容をしっかり押さえておく必要があるようです。
「一般入試と同じレベルの問題が出る学校」もあれば、「基礎的な内容中心」の学校もあるため、志望校の過去問や出題傾向を事前に調べることも重要だとか。
 ライオンさん
ライオンさんなかなかムズイな
教科が限られているとはいえ、日本の学校とのカリキュラムの差を埋め、日本の高校入試に対応する学力レベルまでもっていくのは、簡単ではない気がしますね。
効果的な対策方法:塾?家庭教師?自宅学習?
限られた時間の中で効率よく実力を伸ばすには、個別指導や家庭教師の活用が有効かなと考えています。
私の台湾人の友人のケースでは、ヨーロッパから台湾に帰国したお子さんが高校受験に挑戦する際、家庭教師を2人つけて徹底的にサポートしたとのこと。
聞いたときは驚きましたが、それくらいの覚悟で取り組まないと、現地校と日本の教育の差を埋めるのはなかなか難しいと聞き、いつか我が子も同じ環境になるのかと感じ、今も心に残っています。
もちろん、全ての家庭で同じ方法が必要なわけではありませんが、親の都合で海外生活を余儀なくされている子供たちに、精一杯のことはしてあげたいですね。
帰国子女の進路選びで大切なこと

子どもの進路を考えるとき、どうしても親の目線で「最適解」を探してしまいがちです。でも、やはり一番大切なのは、娘自身の意思。
親としての経験をもとにアドバイスはしつつも、最終的には本人が納得できる進路を選べるようにサポートしたいと思っています。
将来の目標を見据えた進路選択
進路を考える上で大切なのは、目の前の高校選びだけでなく、その先にある大学進学や将来のキャリアまでを視野に入れることです。
例えば、帰国子女枠で受験する場合は、受験科目が少なくハードルが下がる一方で、ある程度の制限が出てくる可能性があります。将来、「TOYOTAに入って車を作りたい!」と夢を語る子に英文科とかはちょっと無いですよね…(笑)。
 ライオンさん
ライオンさん完全に方向間違ってる…
一方、インターナショナルスクールを選べば、英語ベースの学習環境でスムーズに学校生活に入れる反面、日本の大学を目指す場合には追加の対策が必要になることも。
一般入試で日本の高校に進学すれば、選べる学校は増えますが、社会や理科など、帰国子女にとっては不利になりがちな教科にも対応しなければならず、準備期間が短い場合はかなりの覚悟が必要。
このように、どの選択肢にもメリット・デメリットがあります。だからこそ、親が一方的に決めるのではなく、本人にそれぞれの選択肢の特徴や将来の広がりを丁寧に説明し、「自分で選んだ」と思える進路を歩ませてあげることが、なにより大切だと感じています。
ちなみに、私は下のようなスライドを作って、娘に説明してみましたが、「まだ実感わかない」と一蹴されました(笑)。

帰国前・帰国後の準備と心構え
進路を考える上で、試験対策や学校選びと同じくらい大切なのが、「帰国前後の準備と心の整理」です。
まず、帰国前にできる準備としては、日本の教育制度や高校入試の仕組みを親子で理解しておくこと。
正直、私はこれまでそういったことを真面目に調べたことがありませんでした。でも今回、自分が帰国する地域にどんな高校があるのかを調べていく中で、まるで自分がもう一度進路を決めるかのような気持ちになり、ようやく実感を持って考えられるようになりました。
まずは親が理解し、それをかみ砕いて子どもに伝えていくことが大切なんだと、あらためて感じています。
また、心構えの面も軽視できません。海外での生活に慣れた子どもにとって、日本の学校文化や人間関係に適応するのは、思った以上にストレスになることもあります。
だからこそ、帰国のタイミングや目指す進路を早めに定めて、心の準備を進めていくことが大事。そうすることで、娘も気持ちを整えて帰国後の生活に備え、アメリカでの最後の時間も前向きに過ごせるのではないかと、今はそんなふうに期待しています。
まとめ
帰国子女の高校進学には、「帰国子女枠での受験」「一般入試」「編入」「インターナショナルスクール」など複数の選択肢があり、進学先によっては大学受験の可能性や将来の進路に大きな影響を与えることもあります。
だからこそ、それぞれの選択肢と将来の方向性を早い段階で子どもに示し、本人の希望をしっかりと聞いたうえで、最適な進路を一緒に考えていくことが大切だと感じます。
親としてできる最大のサポートは、子どもの選択を尊重しながら、必要な情報と環境をしっかり整えてあげること。正直、悩むことも多いですが…どのような決断であっても、本人の納得のいく道を歩んでいってもらいたいものです。
では、また。



コメント